願われたいのち -「量(はか)り無きいのちの仏」の阿弥陀さま-
長原 真了
布教使 長野市・善立寺住職
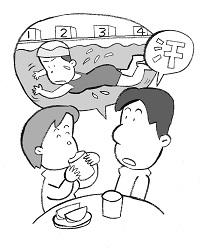
かけがえのない姉
私には、ダウン症の知的障がい者である姉がいます。養護学校(現在は特別支援学校といいます)を卒業後、長いあいだ地元のパン屋さんで働いていましたが、不況の影響で退職を余儀なくされてから今日まで、お寺の手伝いを一生懸命してくれています。
お寺に来られたお客さんへのお茶出しや、お寺の掃除などの大切な仕事、さらには玄関先でのお客さんへの取り次ぎも機転のきいた会話でこなすなど、ちょっとした人気者です。
そんな姉の楽しみは、毎日通う水泳です。スイミングクラブでは、パラリンピックの選手のコースに在籍し、全国大会へ出場してメダルを獲得するほどの本格派スイマーなのです。
ある時、練習を終えてきた姉が、「今日は一生懸命泳いだから、いっぱい汗をかいた」と言いました。私はその言葉に多少の違和感を覚えました。
「だいたい水の中で汗などかくわけがないよ」
そう姉に伝えたのです。すると姉はすかさず、「水の中でも汗は流れるんだよ」と言い返します。はじめのうちは、頑張って泳いでいる気持ちを、汗に重ね合わせて表現しているのだと勝手に理解しましたが、実際のところ、水泳では汗をかくのだそうです。それで、ふと思いました。
姉には、私には見えなかったり、感じられないことを、見えたり感じたりできているのかもしれないと。
思い返せば、姉は時々、外で陽(ひ)の光や風に向かってニコニコしている時があります。まるで光や風とお互いの存在を認め合って会話をしているようです。その姿は、私には見たり感じたりできなくなってしまったもの、見えないけれど確かにあるものの存在を教えてくれていると感じます。
姉は私にとって、大切な家族であり、かけがえのない存在なのです。
願いに生きる姿
一昨年の夏、障がい者福祉施設で19人の尊いいのちが奪われる事件が起こりました。事件後、容疑者は「障がい者なんていなくなればいい」と口述したと聞いて、深い哀(かな)しみと強い憤りとともに、大切な家族の存在が否定されたことは、そのまま自分の存在も否定されたと感じました。そして、社会からの自己喪失を想(おも)い起こさせました。
この事件は典型的なヘイトクライム(憎悪犯罪)といわれますが、そこから見えてくるのは、この事件が特異な思想の持ち主によって突発的に起こされたのではなく、「障がい者なんていなくなればいい」という考え方を育て、受け入れてきた社会構造の背景です。
つまり、この事件は容疑者や関係者だけのものではなく、身近な暮らしの中の問題であり、私たち一人ひとりが向き合うべき問題なのです。
「みんな違って、みんないい」
童謡詩人として知られる金子みすゞさんの言葉です。人それぞれの違いを認めることは、多様性の世界の有り様を受け入れ、そのつながりの中で自分の存在があることにうなずいていくことのはずです。ところが、私たちの人間社会は「善悪」や「損得」で人やモノが判断され、さらにいのちまでもが「役に立つか、立たないか」という有益性によって量(はか)られていく価値観が横行します。その価値観に私が立って、私が苦しみ、私が人を裁(さば)き、傷つけているのです。
「南無阿弥陀仏」とお念仏をいただくことは、「量(はか)り無きいのちの仏」である阿弥陀さまを、私が依りどころにするということです。願いは、相反(あいはん)する現実があってこそ起こされるものです。善悪の善(よ)し悪(あ)しを私の都合によって判断し、いのちを推(お)し量り、その尊厳を大切にできないこの私を阿弥陀さまがご覧になり、救わずにはおけないと、この私を目当てに願いをたてられたのです。
親鸞聖人は、すべてのいのちが阿弥陀さまに願われたいのちであり、そのいのちの尊厳にうなずくとき、お互いのいのちを「御同朋(おんどうほう)」と、共に敬って生きる生き方を教えてくださいました。
いのちの尊厳が簡単に傷つけられていく今だからこそ、私の、人間の小賢(こざか)しさによっていのちを量るのではなく、量り無き大いなるいのちの存在を大切に受けとめ、お互いの違いを認め合い、さらには自らに内在する差別性を見失うことなく問い続けることが、南無阿弥陀仏の願いに生きる姿となるのでしょう。
(本願寺新報 2018年05月20日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。