実りある今 -黙って座ってはいられない仏さま-
米田 順昭
布教使 広島県廿日市市・最禅寺住職
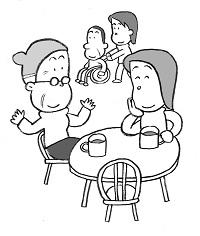
「しあわせ」とは
山のあなたの空遠く
『幸(さいわい)』住むと人のいふ
噫(ああ)われひとと尋(と)めゆきて
涙さしぐみかえりきぬ
山のあなたになほ遠く
『幸』住むと人のいふ
これはカール・ブッセの有名な詩「山のあなた」です。
また、「幸福を探して幸福を見つけた人はいない」という言葉もお聞かせいただきました。
「しあわせ」を、私を離して遠くに求めると、いつまでもしあわせになれないのかもしれません。辞書で「しあわせ」を調べると「仕合わせ」とあり、「めぐりあわせ」を意味していました。
つまり「仕合わせ」とは、今日一日の不思議なめぐりあわせをよろこぶ私、つらいこと苦しいことも多いけれど、今日一日、今一瞬を、尊いご縁であったと味わう私の心を離れてはないのでしょう。
ご門徒さんに、80歳過ぎのお母さんを看病されているお宅があります。
お母さんは若い頃から笑顔がたえず、娘さんたち姉妹とも非常に仲のよいご家庭です。しかし、数年前からお母さんは認知症を患うようになりました。はじめの頃は症状も軽く、自宅と施設を行ったり来たりの生活で、お参りの時には必ずご自宅におられました。
それが最近では、症状が進んだこともあり、施設にいることがほとんどで、お参りのご縁にもあえなくなりました。毎日の看病はお姉さんがされています。少し離れた所に妹さんがお住まいなのですが、距離があるので、月に一度くらいしか看病に来られません。そのような中、昨年末にお参りした時のことです。
その日もお母さんは施設におられ、お参りはお姉さんお一人でした。おつとめが終わると、お姉さんが「妹と母の話をしますと、どうしても病気の話になります。そして、妹は母の看病を私にばかりさせていると、すごく気をつかってくれるんです」と話されました。
それを黙ってうなずいて聞いていますと、続けて「私も当然、病気も気になりますし、看病が大変なときもあります。元気な時の母を思うといたたまれません。でも、私は母に会うのが楽しみなんですよ」と話されたのです。
私が「今も大切な時間なんですね」と申しますと、涙ながらに「そうなんです。母の状態は日によって違います。でも、私が行くとうれしそうにしてくれるんです。時には、私が誰かわからない日もありますが、そんな時でも、『ありがとう。気をつけて帰ってね』と言ってくれるんですよ。母のほうが気をつけなくてはいけないのにね...」とお話しくださいました。
いろんな思いや不安はつきませんが、お母さんの看病の日々は、そのままお母さんとの大切な時間が積み重なっている毎日なのでしょう。いのちに無駄な時間はありません。どんな時もかけがえのない大切な人生です。その方と一緒にいる今一瞬は何より尊い時間であり、元気な時には決して味わえなかった大切ないのちの時間なのです。
空しくない人生を
中国の善導(ぜんどう)大師が、阿弥陀さまのお立ちになったお姿を解釈されたお言葉に、「立(た)ちながら撮(と)りてすなはち行(ゆ)く。端坐(たんざ)してもつて機(き)に赴(おもむ)くに及(およ)ばざるなり」(註釈版聖典七祖篇424ページ)とあります。
「撮(と)りて」とは、つかみとることで、迷いの世界で苦しむ者をつかみとってお浄土につれて行き、仏さまにしてくださるのです。苦しむ者がそこにいれば黙って座っていることができず、立ち上がってその者のところまで来てくださるというのです。
私たちは、苦しみ悲しみを背負い生きています。だからこそ阿弥陀さまは、あなたを救わずにはおれないと、苦しみ悲しみのど真ん中へはたらき出てくださっているのです。それが、この口に現れるお念仏です。
本願力にあひぬれば
むなしくすぐるひとぞなき
功徳の宝海(ほうかい)みちみちて
煩悩の濁水(じょくすい)へだてなし
(註釈版聖典580ページ)
私の人生を空(むな)しく過ごさせない、必ず実りある人生を歩ませてみせる。それが阿弥陀さまの願いです。人生の実りとは、未来にあるのではなく「今・ここ」にあるのでしょう。そのような「いのち」を見る眼(まなこ)を開いてくださるのが、ご本願のおはたらきなのです。
(本願寺新報 2018年03月01日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。