よび声が私の念仏に -逃げるものをほっておけない阿弥陀さま-
満井 秀城
本願寺派総合研究所副所長 広島県廿日市市・西教寺住職
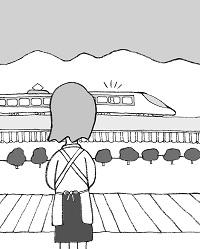
新幹線の車窓に!
ちょうど、入学式や入社式のシーズンです。大学入学や就職では、親元を離れるケースも多いでしょう。親にとっても、子にとっても、期待や不安の入りまじった時期で、いや応なく、親離れ、子離れを意識させられます。
私は、子の立場も経験しましたし、今は親の立場も経験させてもらっています。「子を持って知る 親の恩」とは、よく言ったものだと今になって感じますが、それまでは自分ひとりで大きくなったような顔をしてきました。
私の広島の自坊の真裏には山陽新幹線が通っています。開業時には、境内の約40坪が路線に当たったので、私の感覚では、境内に新幹線が走っているようなものです。
私は、大学が福岡でしたから、帰省には新幹線を利用しました。広島から博多へ向かう下りの新幹線からは、自坊がよく見えます。
ずっと何の意識もなく自坊の裏を通過していたのですが、ある時、ふと懐かしく思って、座席から立ち上がって、車窓から自坊を見た時のことです。新幹線に最も近い本堂の西縁側に、なんと母親が立っていて、こっち(新幹線)を見ているのです。この新幹線に乗っていると見当をつけていたのでしょう。大げさでなく、本堂の縁側に誰がいるか、顔まで見えるくらいの距離を走っていました。その後、大阪の大学院に移ってからは、広島から下りの新幹線に乗らなくなりましたが、大学時代に福岡の下宿に戻る時は必ず母親の姿がありました。
お互い、「見てるからね」とか「見てくれてたんだね」という会話はしませんでしたが、母からすれば、いつまでたっても、不安でしようがなかったのでしょうね。
当時の私は、仏教や真宗に直接関わる学問をしていませんでしたが、正信偈の「大悲無倦常照我(だいひむけんじょうしょうが)」の一句に出あったとき、「ああ、このことかもしれない」と実感したのを覚えています。
目先の欲にとらわれ
阿弥陀さまにとって、この私は、実に危なっかしくてしようがない存在です。ちょっと目を離しているうちに何をするかわからないと、いつも気をもませていたはずです。それが「五劫(ごこう)」という長いご思惟(しゆい)となり、「常照我(じょうしょうが)」という大悲を完成させねばならない必然性だったのでしょう。
親鸞聖人は、この大悲のはたらきである常照の光明について、摂(おさ)め取って捨てないという「摂取不捨(せっしゅふしゃ)」の語を特に尊ばれ、和讃の左訓(さくん)(注釈)に、この語の意味を「ものの逃(に)ぐるを追(お)はへとるなり」(註釈版聖典572ページ脚註)と示してくださいました。阿弥陀さまという仏さまは、逃げ回っている私を追いかけ続けておられます。つまり、自分の方を向いた時だけ救ってあげましょうという仏さまではないのです。真実を見ようとせず、あれがしたい、これが欲しいと、目先の欲にとらわれ、仏縁に背を向け続ける私を、ほっておけないのです。
阿弥陀さま以外の神や仏は、自分の方を向いた時だけ、これだけのことを成し遂げた時だけという、言わば条件付きの救いです。
そのいい例が神社に参拝した時の作法だと思います。私は神社に参拝はしませんが、テレビなどで、そういう場面を見ますと、共通の行為に気がつきます。神前に立つと、まず大きな鈴をジャラジャラと鳴らしています。「ちゃんと来ましたよ。こっち向いてください」という意思表示なんでしょうね。さらに柏手(かしわで)を「パンパン」と2回打ちます。「こっち向いてくださいよ、ちゃんと見ていてくださいよ」という意思表示をして、賽銭(さいせん)を投げ入れるのです。
私たちが、「南無阿弥陀仏」と、お念仏を声に出すのは、「阿弥陀さま、聞いてください」という意味ではありませんね。「南無阿弥陀仏」のよび声となられた阿弥陀さまが、私の念仏の声となってはたらいてくださっているのです。
(本願寺新報 2016年04月01日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。