「おふくろさん」
林寺 脩明
大阪・正福寺住職
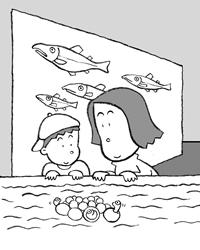
まさに"お袋さん"
「おふくろさん」
私はこの言葉が、人間存在の原点だと思います。混迷をきたしている現今の政治や経済の状況、そして、それによる我欲の狂奔を見るにつけ、今こそこの人間の原点に立ち戻らねば、人類の存続自体が危ぶまれるとさえ、思わざるを得ないのです。
北海道を旅していて、シャケのふるさと館に立ち寄ったことがあります。メスのシャケは産卵の1カ月前ぐらいになると、何も餌(えさ)を食べなくなり、やがて産卵し終えると、1匹残らず死に絶えるのだそうです。
そして、やがて孵化(ふか)したシャケには、それぞれに大きな袋が付着しており、その中には栄養がたっぷりとあり、それを餌としてシャケは成長し、やがて泳ぎ出すというのです。
驚きました。シャケの子どもには母は1匹もいないのです。母に代わる〝お袋〟があるのです。何としたことでしょうか、このカラクリは。まさに自然の妙です。これぞまさに「おふくろさん」です。
牛や馬、犬や猫などの動物はどうでしょうか。産まれると間もなく、ひょろひょろと自力で立ち上がり母親のオッパイにまでたどり着くのです。これがこの動物たちがおのずからいただいているはたらきです。
さて、それでは私たち人間はどうなのでしょうか。〝お袋〟はもらっていません。1年近くは立ち上がることもできません。そのまま放置されるならば、生存不可能なのです。おふくろさん、すなわち育ててくれる者なくしては生きられないのです。ひとりで生きていく術(すべ)は与えられていないのです。お世話をしていただき、だからまたお世話をして生きるいのちというのが、人間存在なのです。いのちの真実なのです。
母は子を抱いて母親となり、子は母に抱かれて子どもとなるのです。しかしはたして今、このように本当に母が子を抱いて育てているでしょうか。豊かで便利な世の中は、親がいなくても子は育つと思い込んではいないでしょうか。言葉もなく、表情も未熟な赤ちゃんは、母親が放置していても、無反応です。だからこそ危ないのです。
母が母となり、子が子となるのは感性の世界です。抱きしめられることで、響き合うのです。体が認知するのです。そして長じては、親は老い、子は育ち、やがて親のお世話をし、そのいのちに寄り添う、これが人間といういのちのありようなのです。
我欲が自らを破壊
かつて、著名な先生が、人間はいかに生きるべきかを語り、人間は「人間していく」ことだと話されたのを耳にしたことがあります。赤ん坊は抱き、老人には寄り添う、これが「人間していく」ことだと私は思います。
また、お世話は、人に限ったことではありません。いのちを育む食べもの、飲みもの、そしてそれらを生み出すはたらき、太陽・水・土などの「めぐみ」。そしてまた身体に与えられた絶妙なる「しくみ」など、すべてにお世話になり、わがいのちを生きているのです。大変なはたらきなのです。どこにも自分のものなどないのです。みんないただきものなのです。
親鸞聖人は如来の慈悲、仏さまのはたらきこそ真実であるとお示しになりました。そこにおいて「人間していく」すがたとは何でしょうか。「有り難う」の合掌です。南無阿弥陀仏のお念仏です。
ところが人間の煩悩・我欲は、わが命、わが思い、わが力だけで生きていると思い込んでいます。そしてそれは、政治、経済の現実の姿となって噴出するのです。領土をめぐり、日本の、韓国の、中国の...と角突き合わせてせめぎあっていますが、一体領土と称する島は誰が生み出したものなのですか? お互いに仲良く寄り添って利用させてもらうのが「人間していく」世界なのではないでしょうか。
しかし、為政者は国防と称して軍事力を誇示し、せっかくいただいたいのちを破滅へと導く愚かさにのめり込もうとしています。すべて我欲に根ざした不自然が、不可思議なすばらしいいのちを滅亡させるのです。
(本願寺新報 2015年07月01日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。