大悲の絆の中で
香川 真二
本願寺派総合研究所研究助手
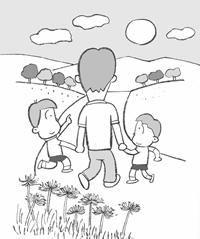
宗派をこえて聴聞
8月に、四国の自坊に帰省しました。京都での生活がとても多忙で、なかなか時間が取れなかったのですが、小学校1年と幼稚園の子どもたちが、リュックサックに宿題や着替えを詰め込んで、「早く帰ろう」と急(せ)かすものですから、渋々(しぶしぶ)応じた感じでした。
お寺に着いて玄関の戸を開けると、懐かしい家の匂いがして、帰ってきたという安堵(あんど)感が湧きました。子どもたちは、早速、自分の玩具箱を持ち出し部屋中に広げたり、おばあちゃんのお手伝いをするといって、本堂の掃除の手伝いに真剣でした。そして水を得た魚のように、蝉しぐれの境内を走り回り、クモがいると大声を上げ、ムカデがいると血相を変えて報告にきたりで、すっかりわんぱく小僧に戻っていました。
自坊では、夏季に4日間、お盆行事として、朝6時から仏典講座が開かれています。『法句(ほっく)経』のパーリ語の原典と、漢文・英語・日本語の諸訳とを読み比べて、お釈迦さまの教えを味わうのです。
参加者の中に、英語、漢文に堪能な方々がおられるので、それぞれ分担して味読し合います。宗派や門徒の別を問わない30人程のグループという雰囲気です。それでも30年以上続いています。
まず「礼讃文(らいさんもん)」を唱和して始まりますが、皆お念仏・礼拝しているのは、ご本尊の阿弥陀さまからのおよび声があるからでしょう。仏法は毛穴から入るものだとつくづく思います。
お彼岸に想う
お盆も終わり、9月はお彼岸。曼珠沙華(まんじゅしゃげ)の花の色を見るにつけても、お浄土に想(おも)いを馳せる時節です。
『仏説無量寿経』には、お釈迦さまが「法蔵菩薩(ほうぞうぼさつ)、いますでに成仏(じょうぶつ)して、現に西方(さいほう)にまします。ここを去ること十万億刹(じゅうまんおくせつ)なり。その仏の世界をば名づけて安楽(あんらく)といふ」(註釈版聖典28ページ)と弟子の阿難(あなん)に説法され、その世界は果てしなく広々として大きく限りがないことを、言葉を尽くして説明しておられます。
なぜ西方か、ということについて、唐(とう)の道綽禅師(どうしゃくぜんじ)は、東は生の始め、西は死の終わりを表し、心の落ち着くところとして西方を選んでいると説明され、善導大師(ぜんどうだいし)は西方を指し示して、煩悩のために心が乱れて安定しない凡人に、正念(しょうねん)を得させるためであるとお示しくださっています。
思いますに、西方は太陽もお月さまも等しく目指す方角であって、懐かしく大恩ある両親や祖父母がまします世界であり、この私もやがて往(ゆ)き生まれる世界でもあります。したがって、私どもの生の依るところ、死の帰するところ、それが阿弥陀さまの西方浄土、さとりの世界と領解(りょうげ)いたします。
大悲の絆
九州の友達から「いのちの絆(きずな)を思う」という法話レターが届きました。
絆とは、絆創膏(ばんそうこう)の「絆」ですから、「つなぎとめるもの」の意です。また、人間関係に用いるときは、人と人との断つことのできないつながりの事実、離れがたい結びつきを指します。英語で言えば「ボンド」です。
「正信偈(しょうしんげ)」をおつとめするとき、ご和讃の第一首目に、
弥陀成仏(みだじょうぶつ)のこのかたは
いまに十劫(じっこう)をへたまへり
(同557ページ)
とありますが、私たちは、すでに十劫の昔から阿弥陀さまの大悲の絆に結ばれていたということに気付かされます。同時に、日々の生活は、報恩感謝の姿勢であるべきですが、散乱にして放逸(ほういつ)の生きざまに明け暮れていることを恥ずかしく思うばかりです。
私どもの暮らしの行事の中に、春秋のお彼岸や、お盆、あるいは報恩講があるのは、阿弥陀さまの大悲の絆を偲ばせていただく、気付きの機会でもあると思うのです。
千載一遇(せんざいいちぐう)の大悲の絆に気付かせていただき、二度とないこの人生を深く顧みて、生かされて生きる今後に思いを馳せるべきでありましょう。
『法句経』182偈をいただいて結びといたします。
「人間の身を受けることは難しい。死すべき人々に寿命があるのも難しい。正しい教えを聞くのも難しい。もろもろのみ仏の出現したもうことも難しい」
(本願寺新報 2012年09月10日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。