同じぬくもりの中で -死にゆくいのちではなく、生まれゆくいのち-
塚本 一真
本願寺派総合研究所上級研究員 佐賀県みやき町・徳常寺衆徒
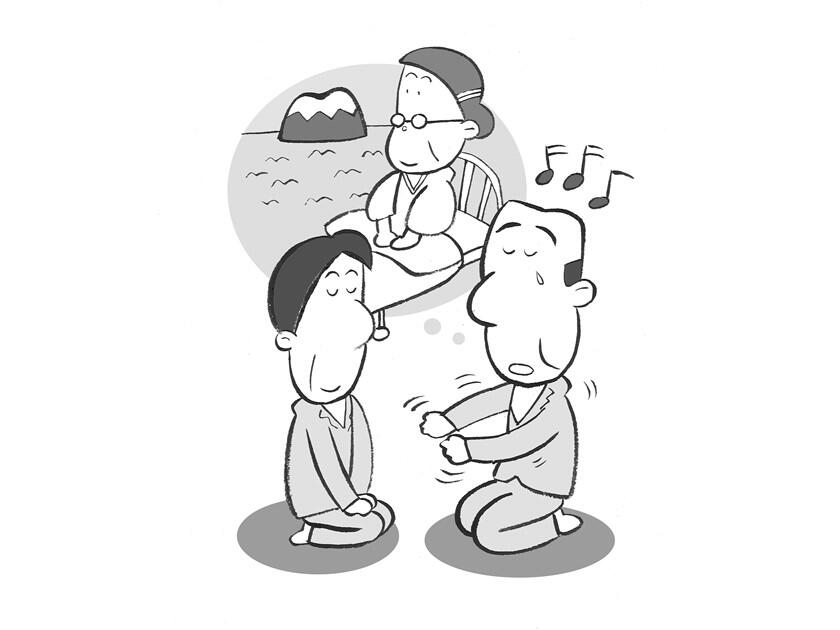
病床で語る言葉
仏法には、先だっていかれた方を縁として、知らされる世界があります。
祖母の記憶を、ほとんど持たない私が、次の話を聞いたのは、33回忌の時でした。
昭和57年の秋。
祖母が手術を受けました。しかし、体調が思わしくなく、入院生活を余儀なくされます。父は、12月に住職継職の法要を控えていました。当然ながら、お寺は忙しさに明け暮れることとなります。その合間をぬって、父は病院を訪れました。そこで聞く祖母の言葉は、すべてが、体と退院後のことです。
「体のきつか」「手足のだるかとよ」「お寺の裏側は、草がワサワサと生えとるやろ、退院したらまず草むしりせんばね」と。それでも、継職法要を無事に終えたとの報告に、祖母は「そりゃあよかった。あんたの七条袈裟(げさ)ばつけた姿を見たかね」と喜びました。
しかし、病は、祖母の体を容赦なくむしばんでいきました。そして、御正忌(ごしょうき)報恩講の明けた1月下旬頃から、病床での祖母の言葉は、だんだんと、その性格を変えていったといいます。
ある時は、集まった孫たちに、「仏さんがね、あんたたちを、まるうしよう、まるうしようと、されよるよ」と声をかけました。また、ある時は、「私は佐賀の町の寺から、田舎の寺に嫁いできて、あれもこれも覚えてきたばってん、何も役に立たんようになったよ...。南無阿弥陀仏、これ一つやった」と口にしました。そして「歌とも詩ともいえない言葉」と看護師さんが表現したのは、「今、私は、如来さまの船に乗せられて、どこを、どう行きよるか、さっぱりわからんばってん、着いたところが向こう岸たい」との語りでした。
最期は歌の一節
2月11日の午前2時頃から、祖母は自らの人生を振り返るように話を始めました。中国の開教に出ていた祖父のもとに、子どもを連れて向かった時の話。終戦で帰国後に、ボロボロになったお寺を建て直そうと苦労した話。お寺の跡取りが決まらずに悩んだ話。子どもの存在が、大きな力になった話。祖母は、戦前・戦中・戦後と動乱の最中(さなか)を、祖父とともに、お寺を護(まも)っていった人でした。
そして、いよいよ最期(さいご)の時。祖母の口から聞こえてきたのは、ある歌の一節でした。
ここは串本
向かいは大島
仲をとりもつ巡航船
アラヨイショヨーイショ...
そうです、「串本節」です。その言葉を聴いたとき、父は祖母が何を言わんとしたか、すぐにわかったといいます。
ここは娑婆(しゃば)だよ
向かいはお浄土
仲をとりもつ南無阿弥陀仏
そこには、阿弥陀さまの船に乗せられて、どこをどのように進んでいるかわからないけれど、安心の中に、生まれていく世界をもった祖母の姿があったのです。
父は「お浄土とは」「お念仏の教えとは」と、弱り衰(おとろ)えゆく母に自分が伝えなければならないと思って病院に通っていたのに、逆に「死にゆくいのちではなく、生まれゆくいのちである」と、そのことを教えてもらったようで、うれしかった、有り難かった、と語っていました。
もちろん、悲しみや寂しさがなくなるわけではありません。それでも、生きることも、死ぬことも、生まれゆく世界も、同じ仏さまのぬくもりの中にある、と言える教えが、今ここにあります。
親鸞聖人は、『高僧和讃』に、
生死(しょうじ)の苦海(くかい)ほとりなし
ひさしくしづめる
われらをば
弥陀弘誓(みだぐぜい)のふねのみぞ
のせてかならず
わたしける
(註釈版聖典579ページ)
と、阿弥陀さまのはたらきを船にたとえられます。
その大いなる船は、乗せるものを選びません。また、乗せるものの能力を問いません。そして、船のはたらき一つで、重いものは重いままに、その性質をかえることなく、向こう岸へと、必ず必ずいたり届けるのです。
私たちは、例外なく、いつか、この世界を離れていきます。その時、地位も名誉も財産も、何一つ持っていくことはできません。海をわたるのに役立つものを何一つ持たないこの私を、ただ阿弥陀さまの船だけが、「のせてかならずわたしける」のです。
(本願寺新報 2019年06月10日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。