家庭の中に仏法を -思い通りにならない人生をお念仏とともに歩む-
石田 慶嗣
旭川龍谷学園理事長 北海道旭川市・慶誠寺住職
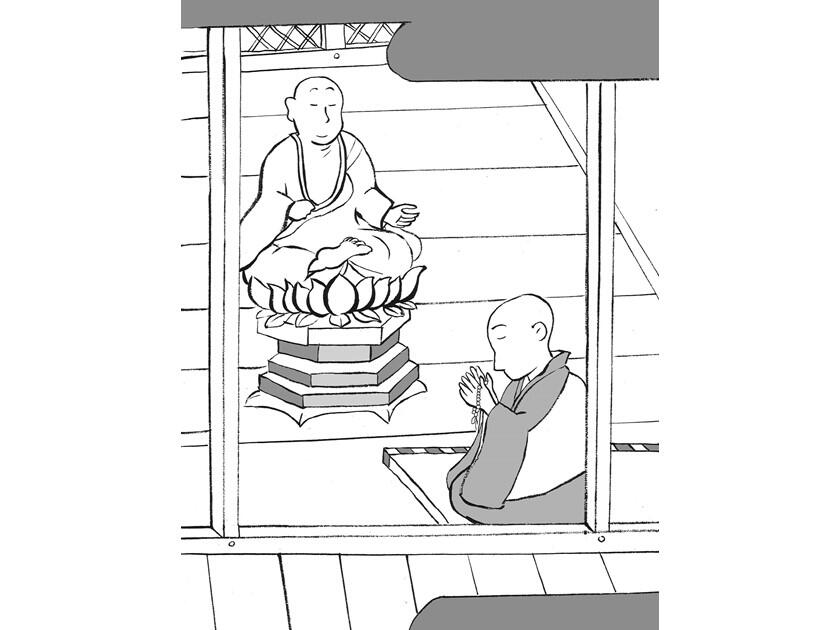
六角堂でのお告げ
最近、いろいろな事件が起こっています。私が住む旭川市でも、ある小学校でバラバラにされたネコが放置され、全国ニュースになりました。
私には、高校1年・中学1年・小学2年の3人の子がいます。まだ小さい末娘がいる親としては、とても心配です。
末娘は、いわゆるパパっ子。いつも「パパ大好き」「パパとお風呂に入る」「パパと寝る」。しまいには、「太っていてもパパ好き」「太っている人の中で一番パパがカッコイイ」と褒(ほ)められているのか、けなされているのか、時々わからなくなります。そんな末娘がいてくれるから、毎日の法務を頑張れるのです。
さて、親鸞聖人の『御絵伝(ごえでん)』の中に、私が好きな「六角夢想(ろっかくむそう)の段」があります。これは、聖人が比叡山で20年の尊い修行をされた後、比叡の山を下り、救世(くせ)観音菩薩が安置されている、京都の六角堂に百日間の参籠(さんろう)をされるお話です。
「六角堂の救世菩薩(くせぼさつ)、顔容端厳(げんようたんごん)の聖僧(しょうそう)の形(かたち)を示現(じげん)して、白衲(びゃくのう)の袈裟(けさ)を着服(ちゃくふく)せしめ、広大(こうだい)の白蓮華(びゃくれんげ)に端坐(たんざ)して、善信(ぜんしん)(親鸞)に告命(ごうみょう)してのたまはく、『行者宿報設女犯(ぎょうじゃしゅくほうせつにょぼん) 我成玉女身被犯(がじょうぎょくにょしんびぼん) 一生之間能荘厳(いっしょうしけんのうしょうごん) 臨終引導生極楽(りんじゅういんどうしょうごくらく)』といへり」(註釈版聖典・千44ページ)と記されています。
六角堂の観音さまは、親鸞聖人に何を言われたのか。
この「女犯偈(にょぼんげ)」といわれるお告げの解釈は諸説ありますが、私は「末世(まっせ)の衆生を救うには、身をもって示さなければダメだ」とお伝えになったのだと思います。いくら凡夫(ぼんぶ)が救われる。在家のまま、煩悩の身のままで救われると説いても、末世に入った今は、それではもうダメだというお示しでしょう。
「真実の仏法を伝えるために、あなたも結婚しなさい。肉食妻帯(にくじきさいたい)しなさい。あなたが妻を持ち、子に迷いながら、家庭の中に仏法を聞き開いたならば、それこそが末世の明かりとなるでしょう」と言われたのではないでしょうか。
あたり前の反対派
なるほど、今の自分をこの場面に置き換えてみたら、よくわかります。私は、この六角堂の場面が大好きです。最初にこのお話を聞いた時、「浄土真宗の僧侶として親鸞さまのみ教えを仰(あお)がせていただいてよかった」と思った瞬間でもありました。
自分も、3人の子を持つ親です。もちろん妻はひとりですが...。その妻と結婚して生活を始めると、たわいもないことでけんかをしてしまいます。
私が作った料理に「しょっぱい」「味が濃い」などと言われて、腹の立つ自分がいます。どうして、「ご飯を作ってくれてありがとう」と言ってくれないのだろうかと思う自分がいます。
でも考えてみると、私も、妻に「ご飯を作ってくれてありがとう」と言ったことがありません。いつの頃からか、妻が食事を作ってくれていることが、あたり前になっていたのです。あたり前は、あたり前ではないことに気づかせていただきました。
あたり前の反対は、有り難し。「ああ、妻よ、有り難う」と心の中で叫んでいる自分がいます。でも、声に出して言えない私もそこにいます。声に出して言えたら、今よりもお互いの生活はより楽しくなるのに、面と向かって言うことの恥ずかしさが邪魔をするのです。
子どもたちも同じでしょう。「勉強しなさい」と言われても、言われることに反発して勉強しない子。ゲームばかりしているから、叱られる子。すべて親の立場での考えに過ぎません。こうして、親は思い通りにならない子どもたちを見て悩むのです。
親鸞聖人には、そのような悩みを持ちながら、思い通りにならない人生を歩ませていただき、それでも拯(すく)われていくという姿を身をもって示していただいたのだと思うと、私の心はスーッと気持ちが楽になってきます。
こうした人生の苦しみに直面する中で、お釈迦さまは、私たちが苦しみを感じてしまう原因を探求されました。私たちは、苦しみの原因をつい自分を取り巻く環境にあると考えます。しかし、実は苦しみの原因は、この私自身にあったのです。
自分自身の煩悩のせいで闇に迷うのが、私たちのありさま。そんな煩悩の闇に迷う私たちに、何とかして拯(すく)いを与えようと、今ここではたらいておられるのが阿弥陀如来です。
親鸞聖人が身をもってお示しくださったお念仏のみ教えを通して、今の私たちが拯われるのです。
(本願寺新報 2019年11月01日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。