終わりなき迷いの果て -無量の光に照らされて仏道を歩む-
加藤 真悟
布教使 大阪府四條畷市・自然寺住職
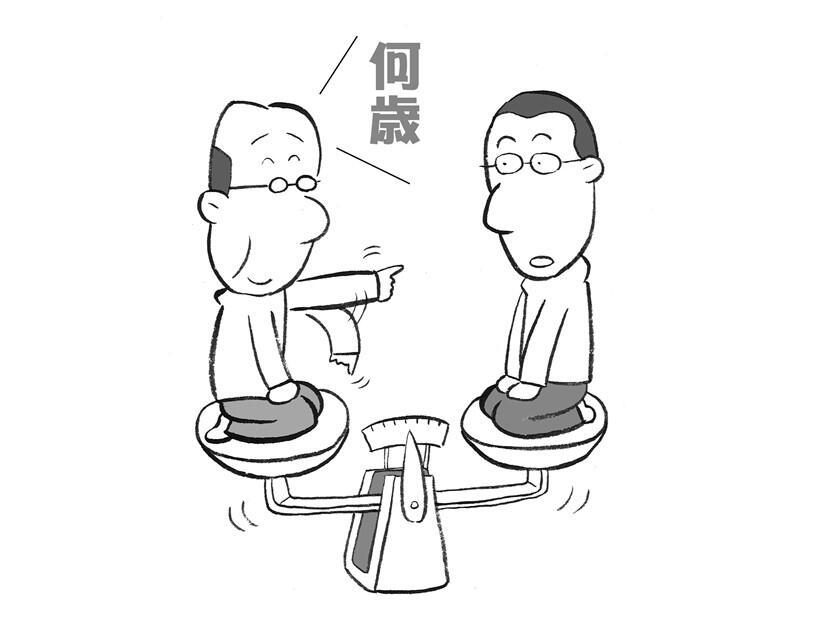
年齢ではなく
「若院(わかいん)さんは、いくつになりはったんかいな」
かつて、会うたびに、私の年齢を尋ねる方がおられました。何度も年齢を聞かれるので、私は当初、「いいかげん覚えてくれへんかなぁ」と思っていました。
ところが、実はその方が、私の年齢を知りたくて尋ねておられるわけではなく、ご自身の老いについての思いを話したいと思っておられることに、後になって気がつきました。
「若院さんは若うてよろしいなぁ。若いことが一番ですわ。それに比べて、私みたいに年取ってしもたらあきまへんで。はよお向こうへ行かしてほしいぐらいですわ」
この言葉が、私の年齢を聞いた後に、いつも続いていたのです。それに対して私は、「年を取っていくと、思い通りにならんことが、いっぱいあるんですねぇ。なかなか今の僕にはわからへんけど、それでも、もう少し一緒にいてくれはると、僕はうれしいんです」と応えていました。
それと同時に、「いつ亡くなってもいいようなことを言いはるけど、この人、しっかり三度三度ご飯食べて、病院通って、診察受けて、もらった薬も忘れずに飲んで、出かける時にも薬持ち歩いてはるんやもんなぁ...」などと、その方が懸命に生きようとする姿が垣間(かいま)見られることに、人間の持つ矛盾や滑稽(こっけい)さを感じたりもしていました。
そんなある日、この方がお出かけの様子でしたので、どちらへ行かれるのかお尋ねしました。すると、「同窓会に行く」と言われます。
「会うのは10年以上ぶりかなぁ。うれしいですわぁ。年は取らせてもらうもんですなぁ」と、感慨深げに言われるのです。
そしてさらに、「若院さんみたいな若い人に、この感動がわかるかなぁ」とも言われました。
「この前は、若いのが一番、年取ったらあかんって言わたはったのに、今回は、年を取ることを喜んでおられるんやなぁ」と、少し苦笑いをしながら聞いていました。
尺とり虫のよう
さて、私たちは若さと老いの、どちらを歓迎すべきなのでしょうか。あるいは、生きていることと死にゆくことの、どちらを肯定すべきなのでしょうか。
お釈迦さまは「世俗のことがらに触れても、その人の心が動揺せず、憂(うれ)いなく、汚れを離れ、安穏であること―これがこよなき幸せである」(『スッタニパータ』)と言われました。
あらためて私の心の中をかえりみますと、世俗のことがらに触れては、絶えず動揺を繰り返しているように思えます。何を歓迎し何を拒否し、何を肯定し何を否定すべきか、その物差しがコロコロと変わり、揺れ動いているように思えるのですが、皆さんは、いかがでしょうか。
七高僧(しちこうそう)の第三祖・曇鸞(どんらん)大師は『往生論註(ろんちゅう)』で次のように述べられています。
「仏本(ぶつもと)この荘厳清浄功徳(しょうごんしょうじょうくどく)を起(おこ)したまへる所以(ゆえん)は、三界(さんがい)を見そなはすに、これ虚偽(こぎ)の相(そう)(中略)尺蠖(しゃっかく)の循環するがごとく、蚕繭(さんけん)の自縛(じばく)するがごとし」(註釈版聖典七祖偏57ページ)
曇鸞大師は、阿弥陀さまが本願を起こされたのは、動揺するこの私のためだと言われます。尺蠖とは尺とり虫、蚕繭とは、かいこのまゆです。
私たちは迷いの世界を果てしなくめぐり続けているのですが、それはちょうど、尺とり虫が一本の棒の上を行ったり来たりして、その終わりがないように、そして、かいこが自分の糸で自らを縛るように、迷いの世界に自らを煩悩で縛っているのです。
私たちは確かな物差しを持たず、安穏なることなく、止まることを知らず、ずっと揺れ動き続けているのです。
阿弥陀さまは、この揺れ動く私のいのちを正しく導くために、揺れ動くことのない確かないのちの世界、浄土を建立されました。
浄土は無量の光の世界です。老若(ろうにゃく)・生死(しょうじ)のどちらかに光が当たり、歓迎されたり拒否されたりするのではなく、また、どちらかが肯定されたり否定されたりする世界ではなく、いずれにもその光をもって、一つ一つが、かけがえのない、尊いことであると示されるのです。
生死に、老若に、あるいはさまざまなものの間を、揺れ動きながら生きるこの私が、浄土を真実の世界と仰ぎ、確かな寄る辺としながら生きる時、それが私にとっての安らかなる仏道となっていくのです。
(本願寺新報 2020年11月01日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。