三奉請と十三回忌 -変わらないみ教えに導かれてお念仏に遇う-
金澤 豊
仏教伝道協会職員
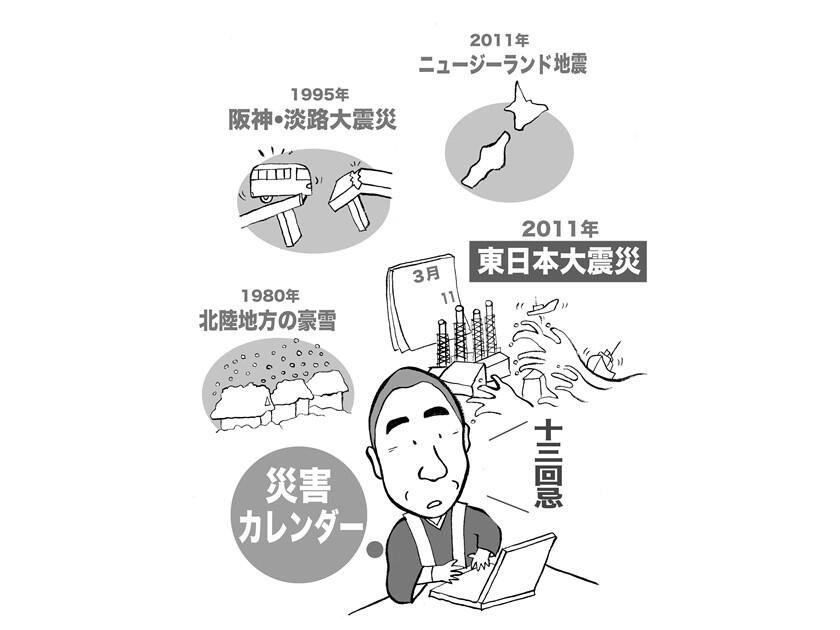
インターネットの「お気に入り」ページに 「災害カレンダー」というサイトをマークしています。「過去の教訓を未来につなぐ」というキャッチコピーで、過去から現在に至るまで世界中の大災害を網羅しているカレンダーです。
例えば、1月17日は1995年の「阪神・淡路大震災」だけでなく、その1年前にカリフォルニア州ロサンゼルス近郊を震源とした「ノースリッジ地震」の日でもあることが確認できます。また、2月は28日間のうち、1980年「北陸豪雪」、1822年「有珠山噴火」、2011年はニュージーランドでの大地震、1949年「能代大火」など、23の出来事が記録されています。
今日は何の日なのかと1日1日を見ると、災害の規模や被害の状況、亡くなられた人数まで記載されています。長い歴史のうえで、年は違えどもほぼ毎日、どこかで大きな災害が起こってきたという未知の事実に驚かされます。過去に起こったことを忘れずに、我がこととして想像したり、防災意識を高めたり、街の歴史を知るという教育的効果もある有用なページだと思います。また、有用と思う以上に「災害の起こった日」とは、多くの人が亡くなった日であり、ご遺族にとっては大切な方の命日なのだということを思わされます。
2011年3月11日に東日本大震災が起こりました。今から12年前のことです。3月11日は一周忌、三回忌、七回忌と三陸沿岸部の被災地で思いを寄せ、屋外で法要をさせていただきました。それぞれに忘れ難い記憶です。
また、法要をつとめたのは3月11日だけではありません。3月末に仮設住宅の中で「遺体を発見した日が命日だと思っている」とおっしゃる方から依頼されてつとめた法要。さらには「母親が見つかった場所で法事をしてほしい」と吐露された方に案内してもらい、流出した家の跡地でお参りをした経験もあります。そのようなご遺族の思いを引き受け、仏さまとのご縁を確認していただく場でのおつとめは、いつも「三奉請」からでした。
奉請弥陀如来 入道場 散華楽 奉請釈迦如来 入道場 散華楽 奉請十方如来 入道場 散華楽
「三奉請」はもともと善導大師が著された『法事讃』の一節にあたります。
善導大師のお考えを大切にされた法然聖人は、後白河法皇の十三回忌の仏事に際して、本書に依って儀礼をつとめられたそうです。また、親鸞聖人のひ孫に当たる覚如上人も、父である覚恵上人の十三回忌に『法事讃』を修行された記録が残っています。阿弥陀如来、釈迦如来、十方の如来とのご縁をいただく「三奉請」の響きは、過去から今もご遺族の心にはたらき続けているのです。
まもなく迎える3月11日は、東日本大震災の十三回忌にあたります。直接的な遺族ではない私にとっては、支援活動に関わる中でさまざまな出会いと別れを経てきた12年間でした。思い出す出来事よりも、もう思い出せない事柄の方が増えてきたような気がします。それでも3月11日が近づくと、どうしても落ち着いておられず感情が動きます。12年が経つ今でも、心を寄せる場所が見つからないという岩手県沿岸部の友人のこと。当初から私たちの支援活動を気にかけてくれて往生された先輩僧侶のこと。「浄土真宗さんの三奉請を聞かせてもらうと気持ちがキリッとする」と事あるごとに言ってくれた、今は亡き曹洞宗の友人僧侶のこと。多くの人を思い出し続けながら、2023年の今の自分に出来ることを考え行動します。
年回忌法要がおつとまりになる中で、ご遺族にとって変わる心情もあるでしょう。あるいは何年経とうとも変わらない悲しみもあります。そんな定まらない心を持つ私たちだからこそ、救わずにはおれないと、仏さまははたらきかけてくださいます。仏さまのお慈悲は決して変わることなく、悲喜こもごもの人生を歩む私たちに注がれます。
私自身取り組んできた復興支援活動の中でも、大きく気持ちが揺さぶられ、あれで本当によかったのかと、いまだに逡巡することがあります。すべての苦悩を抱えた人のために寄り添う活動が到底完遂できない私です。そのような私だからこそ、東日本大震災の十三回忌の法要も「三奉請」から始まる変わらないみ教えに導かれて、お念仏に出遇わせていただきたいと思います。
(本願寺新報 2023年03月01日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。