「よかった よかった...」-亡き父とともに聖人のお導きをよろこぶ-
渡辺 梯爾
三重大学名誉教授・三重県四日市市・善正寺住職
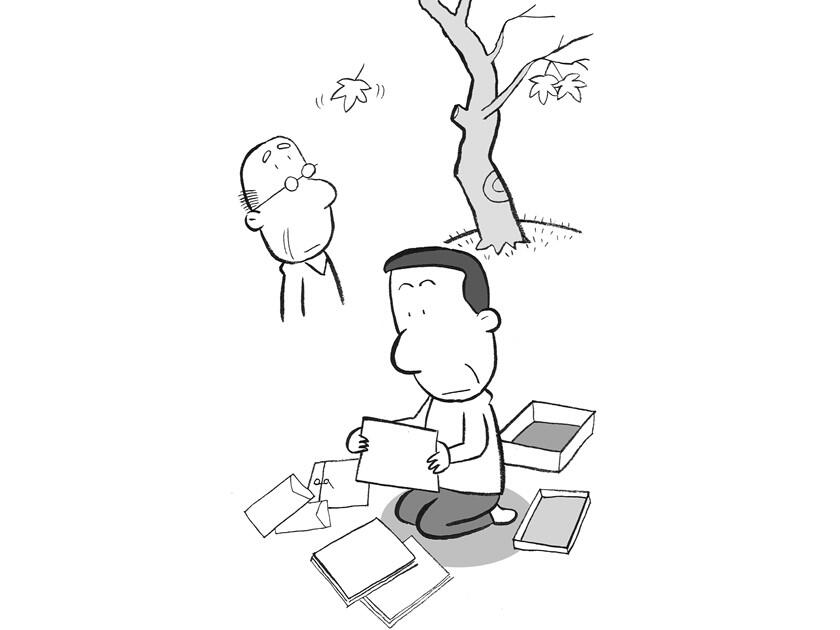
すべて『教行信証』
皆さんは、3月29日から始まった親鸞聖人御誕生850年・立教開宗800年慶讃法要にお参りになられたでしょうか。
このたびの慶讃法要のおつとめは御本典、『顕浄土真実教行証文類』(教行信証)の「総序」のご文で始まります。
「ああ、弘誓の強縁、多生にも値ひがたく、真実の浄信、億劫にも獲がたし。たまたま行信を獲ば、遠く宿縁を慶べ」(註釈版聖典132㌻)との感動的なお言葉です。
「ああ、この大いなる本願は、いくたび生を重ねてもあえるものではなく、まことの信心はどれだけ時を経ても得ることはできない。思いがけずこの真実の行と真実の信を得たなら、遠く過去からの因縁をよろこべ」と、親鸞聖人はおっしゃってくださるのです。
「総序」のご文に続いて、お導師が法要の意義を明らかにする「表白」を述べられ、おなじみの「正信偈(御本典・行巻)」。そして最後に御本典「後序」のお言葉です。
「慶ばしいかな、心を弘誓の仏地に樹て、念を難思の法海に流す。深く如来の矜哀を知りて、まことに師教の恩厚を仰ぐ。慶喜いよいよ至り、至孝いよいよ重し」(同473㌻)。
「まことによろこばしいことである。心を本願の大地にうちたて、思いを不可思議の大海に流す。深く如来の慈悲のおこころを知り、まことに師の厚いご恩を仰ぐ。よろこびの思いはいよいよ増し、敬いの思いはますます深まっていく」と聖人はいわれます。
このように今回のご法要のおつとめ「新制 御本典作法」は全て 『教行信証』のお言葉です。この『教行信証』に記されている「元仁元年」(1224)、親鸞聖人52歳の年が浄土真宗の「立教開宗」と定められています。
ご本山の御影堂で一緒におつとめをさせていただきながら、「親鸞聖人のお導きに遇えてよかったなあ」と、わが宿縁をかみしめ、亡父のことを思い起こしていました。
恩徳讃を歌いつつ
私の父は、33年前に86歳で往生浄土の素懐を遂げました。亡くなる2日前の夜、私と坊守に、「親鸞さん...、よかった、よかった...」と、ほのかに笑顔を浮かべて言ったのです。晩年、大腸の手術で人工肛門を装着し、老衰による自宅介護の中で最期の時を迎えましたが、私は「親鸞さまの何がよかったのか」と考え続けました。
亡くなる半年前のこと、父が会長を務めていた全国布教同志会の全国大会が本山で開催され、老衰の進む父と共に3日間過ごしました。私はきっと「最後にご本山にお参りできた。そして親鸞さまにお礼を申すことができたのがよかったのだろう」と当初は想像していました。
ところが、父が亡くなった後に、父の布教ノートや原稿などの中から、毛筆の「遺書」らしきものが見つかりました。それは、辞世の句と人生の結語でした。
素 懐 釋 尚爾 冬もみじ 母なる土に 召され往く 散りて土にかえる 是自然なり 浄土の往生 是必然なり 願力無窮にして自然 ああ有り難き哉
晩秋の頃、父はいよいよこの世の命終える時が近いことを自覚し、散り急ぐ冬もみじにわが身を重ね合わせて「散りて土にかえる身」と思い至ったのでしょう。それは、わがはからいのおよばない自然の理である。それが同時に、如来さまの窮まりなき願力のゆえにお浄土に往生させていただくのが必然の理である。自然にして、必然のおすくいとは何と有り難きことであろうかと...。
これは『正像末和讃』の末尾に収められている「親鸞八十八歳御筆」にある「自然法爾章」のお言葉によるもので、親鸞さま最晩年の信仰の深まりに自らの領解を重ね合わせてつづったのだと推察されます。すると、「親鸞さん...、よかった、よかった...」という父の最後の言葉は、「親鸞さまのお導きに遇えてよかった」ということなのだ、そう読み取ることができました。
「如来大悲の恩徳は 身を粉にしても報ずべし 師主知識の恩徳も ほねをくだきても謝すべし」と「恩徳讃」を皆さんと歌いつつ、私も「遇えてよかった 親鸞さま」の思いを一層深くさせていただいたのでした。
(本願寺新報 2023年05月10日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。