改悔批判を迎えて-「まかせる」ところで「自力がすたる」-
満井 秀城
本願寺派総合研究所長・広島県廿日市市・西教寺住職
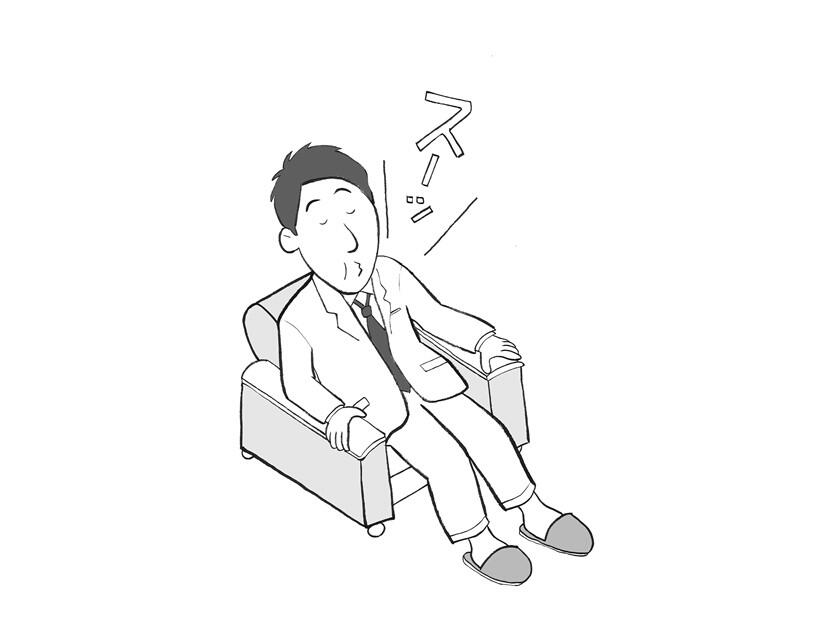
「自力心」を悔いる
本年も9日から16日まで御正忌報恩講の法要がご修行中です。期間中、13日を除く6日間、初夜勤行の時に「改悔批判」が行われます。どんな内容かご存じでしょうか。
「改悔」とは、漢文的には返り点を打って「悔いるべきを改める」くらいになるでしょう。私たちの「悔いるべき」事柄とは何でしょうか。キリスト教などで、「悔い改めよ」と懺悔するのと同じでしょうか。
他宗教・他宗派の懺悔は、自己の罪業性に対する懺悔で、悔い改めるべきは、私たちの罪深さを指します。
「私は、昨日こんな罪を犯しました」と告白するのです。
自己の罪業性に向き合うことは大事ですが、私たちの阿弥陀さまは、どんな悪人も漏らさず救ってくださいます。阿弥陀さまに対して悔いるべきは、ご本願を疑う自力心のみです。
自力と言っても、そんなに悪いことをしているわけではないのだから、悪人をも見捨てない阿弥陀さまなら、自力くらい大目に見てくださればと思うかもしれませんが、そうはいきません。自力は本願を邪魔する行為です。
自力は、何より私たち自身の後生の一大事に対する妨げになるとともに、他者に対しても誤った理解を振りまいて、他者を妨げています。このことを善導大師は、「自障障他」(註釈版聖典七祖篇660㌻)とおっしゃっているのです。
私たちの悔いるべきは、この自力心です。自力心との決別こそが、「改悔」の内実に他なりません。つまり、自力心と決別し、他力に帰入することを表明する儀式が「改悔批判」なのです。
お慈悲にゆだねる
次に、自力心との決別と他力への帰入の関係性が問題になります。通常、私たちの感覚では、まず自力心を決別してから他力に帰入するという前後関係を想定しますよね。例えば、蓄財のためには、まず借金の返済が先だと考えます。ところが、阿弥陀さまのお救いは、私たちがまず借金を返してから、その後で功徳を与えてくださるのではありません。
『観無量寿経』の九品段という一段に、「下々品」では、私たちの罪を「八十億劫の生死の罪を除く」(註釈版聖典116㌻)とありますが、「下上品」では「五十億劫の生死の罪を除く」(同113㌻)とあります。これは、念仏の功徳が人によって違うということなのでしょうか。
ある若い恋人同士がいました。彼女には人に言えない負い目があり、このまま深入りすると別れがつらくなると思い、彼とは常に距離を保って、深入りしないよう自制していました。ところが、お互いのひかれる思いは日に日に募り、ついに彼が結婚のプロポーズをします。彼女は、うれしいとは思いつつも、本当のことを彼に告げます。
「今まで隠してたんだけど、私には1000万円の借金があり、マンションのローンも残ってて」と告白するのです。彼も、よそよそしい態度は気になっていたのでしょう。こう返答します。
「何だ、そんなことか。そんなら僕が全部引き受ける」
抱えている借金は人それぞれで、それが「五十億劫の罪」と「八十億劫の罪」との違いです。そんな個別の事情など関係なく、「全部、私が引き受けた」が、阿弥陀さまの救いです。
「自力心との決別」が先で、それが済んでから「他力に帰入する」となれば、自力との決別という私の仕事が前提になってしまいます。これだと、何らかの自力が入ることになり、他力の法義にはなりません。
そもそも、私たちが、自分で自力を消すことができるでしょうか。「また自力が出た」「また自力が出た」と、自分で自力を消し続けていったとしても、最後まで捨てる自分が残ります。すなわち、自分で自力を捨てようとしても、この迷路から永久に抜け出せません。
「疲れたなぁ」と帰宅した時、ゆったりしたソファーに身を委ねたら、自然と肩の力がスーッと抜けます。それと同じように阿弥陀さまの大きな大きなお慈悲に身を委ねた時、自ずから自力が抜けているのです。
自力心との決別と他力への帰入とは、まったくの同時。まかせるところで自力がすたる。この変革の儀式が「改悔批判」です。蓮如上人以来、連綿と続いてきた、この儀式を、今年も大切にしてまいりたいと思います。ぜひ、本年の御正忌報恩講、そして改悔批判にもご縁を結んでください。
(本願寺新報 2024年01月10日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。