石ころも黄金のように-アンベードカル博士と親鸞聖人-
志賀 浄邦
京都産業大学教授・大分県竹田市・常證寺住職
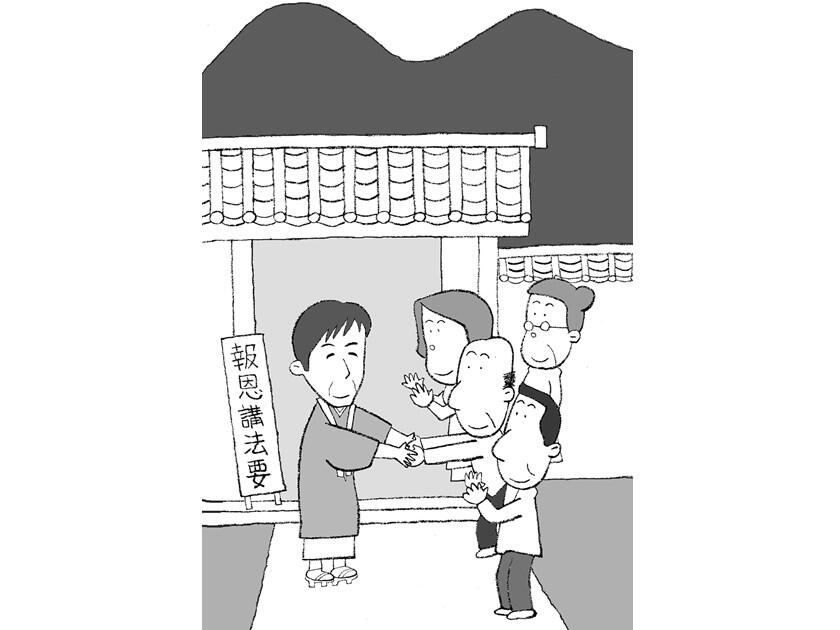
インドの仏教徒
インドのナーグプルという町を訪れたときのことです。現地にあるインドーラ寺という仏教寺院では朝のおつとめが行われており、堂内にはパーリ語の「三帰依」を唱和する人々の声が響き渡っていました。その声は私の心と体にいや応なく染み込んできて、あたかもブッダ在世当時にタイムスリップしたような感覚を覚えました。
インドでは13世紀頃に滅亡したとされる仏教は、20世紀半ばにビームラーオ・アンベードカルという人物によって復活を遂げました。
アンベードカル博士、そして博士と共に仏教に改宗した数十万人の人々の多くは、歴史上「不可触民」と呼ばれてきた民衆で、インドの約8割を占めるヒンドゥー教徒から苛烈な差別を受けてきました。
彼らはアンベードカル博士に従って、万人の平等を説く仏教に改宗する道を選び、その後は仏教徒として生きることを通じて人間としての尊厳を取り戻すことができました。
ナーグプルでは、ブッダの教えを心の依りどころとして前向きな人生を送り、社会で活躍する多くの方々に出会いました。現地の仏教徒と交流する中で、ふと親鸞聖人の次の言葉が思い出されました。
「れふし・あき人、さまざまのものはみな、いし・かはら・つぶてのごとくなるわれらなり。(中略)いし・かはら・つぶてなんどをよくこがねとなさしめんがごとしとたとへたまへるなり」(註釈版聖典708㌻)
親鸞聖人は、道端に落ちている石ころや瓦礫が、まるで黄金になるように、煩悩を抱えた私たちも、阿弥陀さまの摂取不捨の光に照らされることによって光り輝き、そのままの姿で救われていくとおっしゃられました。
親鸞聖人もアンベードカル博士も、常に民衆の側に立って人々の苦悩に寄り添い、共に生きることを大切にされるお方でした。
報恩講をつとめて
さて、毎年のことですが、昨年も報恩講のおつとめを無事に終えることができました。私が住職を務めるお寺は大きなお寺ではありませんが、新型コロナが一段落したこともあって多くの方々が参拝してくださいました。
若い頃は正直なところ、過疎化と少子高齢化が進んだ、こんな田舎の小さな山寺に存在意義などあるのだろうかと思い悩んだ時期もありました。でも、「ささやかながらある」。それが、インドでの体験を通じて私が導き出した答えです。
インドには寺院が少なく、礼拝所のような小さなスペースであっても、信仰の拠点として貴重な場となります。お寺が地域の人々の交流の場となっているだけでなく、お寺の存在そのものが民衆の心の依りどころになっています。これらのことの多くは日本の地方寺院にも当てはまるのではないでしょうか。
私たちはたとえ社会から見放され石ころのような存在として扱われたとしても、み仏の智慧と慈悲の光に照らされて光り輝く唯一無二の存在なのです。アンベードカル博士の仏教と浄土真宗とでは教理面で異なる点も多いのですが、インド仏教徒の活き活きとした姿を目にするにつけ、み仏の光に対する思いは共有することができると感じました。
先代住職の父が往生してからは、報恩講のおつとめも一人で行わなければならなくなりました。それまでは父に頼りきりでしたので、とても不安でしたが、いざ法要が始まって正信偈を読み始めたとき、はたと気づいたことがありました。
「亡き父は、お浄土から今日もこの場にお参りしてくれているのだから、父が健在であった時と同じようにおつとめすればよいのではないか」
その時、不思議なことに、朗々と正信偈を読む父の声が聞こえてきたような気がしました。さらに、これまでお寺を大切に思い護ってきてくださったかつてのご門徒の方々や、歴代の住職方も姿は見えないものの、お浄土からこの世に還り来て参列し共にお念仏を申してくださっている、そのような情景が目に浮かびました。自然と感謝の気持ちがこみあげ涙があふれてきました。
これまで教義としてしか理解できていなかった「還相回向」のみ教えを、身をもって実感することのできた瞬間でした。
(本願寺新報 2024年01月20日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。