「きく」という生き方-阿弥陀さまの願いを聞き、自分の姿を振り返る-
吉本 光俊
京都府久御山町・大光寺住職
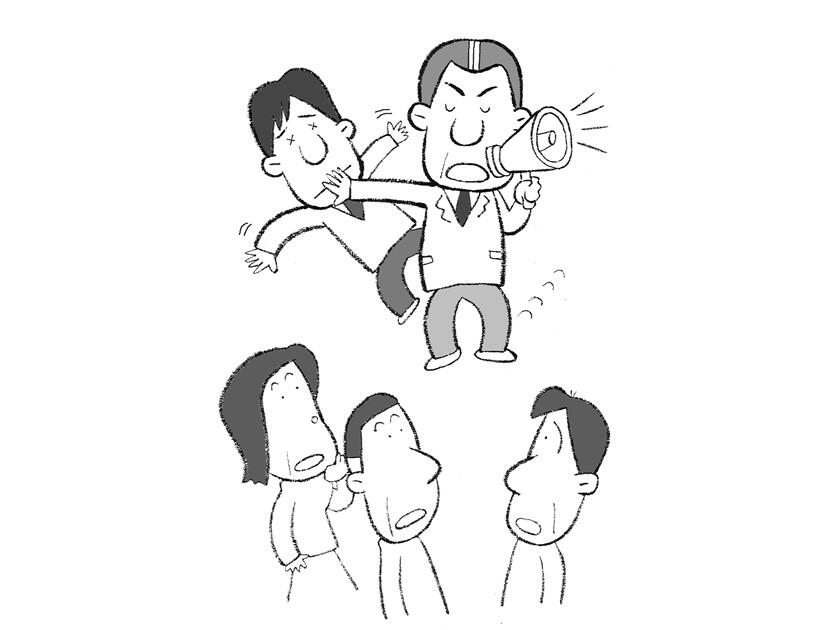
相手に共感して
私たちは、ふだん人の話を本当によく聞いているでしょうか。
もしかしたら、相手の言うことに熱心に耳を傾けることよりも、自分の話を人に聞いてもらいたいという欲のほうが勝っているのではないでしょうか。
あるいは自分にとって都合のよいところや興味深い部分だけを耳に入れ、そうじゃないところに対しては、耳を閉ざし排除するというようなことをしていないでしょうか。
古代ギリシャの哲学者・ゼノンは、自分が話すことの倍、相手の話を聞かなければいけないと言っていますが、やはり、人の話をよく聞くことの大切さを教えてくれているのでしょう。
ちなみに、「きく」には「聞く」と「聴く」という漢字表記があります。
「聞」は音が自然と(意識せず)耳に入ってくること。
「聴」は部首に「心」という字があることからもわかるように、心をこめて意識して耳を傾けること。
そういう違いがあるそうです。
「傾聴」という言葉があります。自分の意見をはさんだり、批判や反論もせずに、相手の話に耳を傾けることに徹するという意味になるでしょうか。これは相手の立場に立ってその人に共感しながら、そしてその人の意見を肯定しながら、ただひたすら聞くということでもあり、特にビジネスや介護の現場においては大変重要なスキルとされているそうです。
浄土真宗の門徒にとっては、「聴聞」が特に大切だといわれています。仏さまのみ教えをよく聞くこと。お念仏のよび声を真摯に心から聞くこと。
傾聴であれ、聴聞であれ、その根底に共通してあるものは、相手の話を素直に聞き、ひいては相手の存在そのものまで、そのまま受け入れていくという一つの姿勢ではないでしょうか。
ひたすら耳を傾け
みなさんもご存じの通り、親鸞聖人はお若い頃、比叡山で仏道修行をされていました。そこでは自身の迷いを断ち切るために、さまざまな行にいそしまれたはずです。
また、当時の比叡山は、学問が盛んに行われている日本で最高の仏教研究機関の一つでした。今でいえば有名大学のような最高学府に相当するでしょうか。親鸞聖人はそこで仏教思想も探究されたはずです。いわば当時の「知」と「仏道修行」を究められたことでしょう。
しかし、そのような親鸞聖人であっても、何か心の中にあるもやもやっとしたものを取り除けなかったのです。
そこで法然聖人のもとに赴き、師のお導きによって本当の意味でお念仏のみ教えに出あわれることになるのです。
お念仏というものがいかに素晴らしいものであるのか。お念仏はいかなる行にも勝り、お念仏を称えるのに余計な知識などはいらない。なぜならお念仏は阿弥陀如来から私たちに与えられるものだから...。
ここで想像するのは、師である法然聖人が語りかける本願のみ教えに、ひたすら耳を傾ける親鸞聖人のお姿です。子どもが何かの遊びに熱中して無心になっているかのごとく、師の口から出てくるお念仏のみ教えをただ素直に全身でもって受け入れていこうとされる聖人のお姿です。
何をやっても救われる道を見いだせなかった自身の前に師が説き示されたお念仏のみ教え。その一つの道を疑いなく歩んでいこうとされる親鸞聖人の固い決意。
あるいは、阿弥陀如来の大きな慈悲のみ心に照らしだされ、そこであらわになった自分の心を見つめ直される親鸞聖人の視線。
そして阿弥陀如来の本願と出あえて歓喜に包まれた聖人のお顔を心に思い描いています。
そのような親鸞聖人のお姿を思いますとき、私たち浄土真宗の門徒は、お念仏のよび声を聞かせていただき、阿弥陀さまが私たちに対して願われていることを、心して聞いていくことが本当に大切なのではないでしょうか。
お念仏は、私たちにとって鏡のような存在でもあります。お念仏のみ教えを聞かせていただき、そこに映し出されるわが身を絶えず振り返り自ら反省していく。そういう生活の中に、仏教徒としての謙虚な生き方があるのだと私は思っております。それが「きく」という生き方ではないでしょうか。
(本願寺新報 2024年03月01日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。