「二の矢」を受けない生活-煩悩を消すことなく念仏申す暮らしの中で-
河智 義邦
岐阜聖徳学園大学教授・島根県邑南町・明賢寺住職
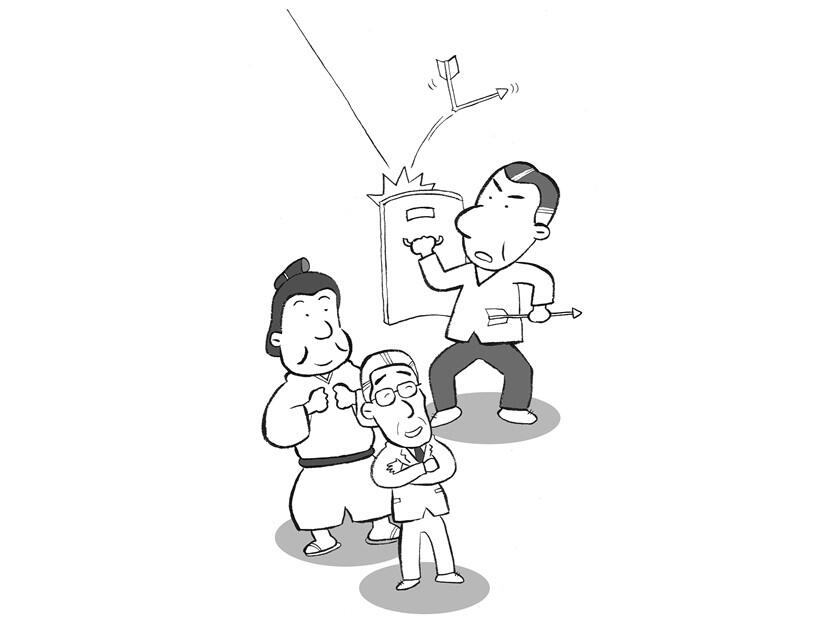
どう生きていくか
今春は寒の戻りも手伝って、満開の桜に彩られて入学シーズンを迎えることができました。桜は日本文化を象徴する花として世界でも知られていて、俳句も多く詠まれています。
散る桜 残る桜も 散る桜
良寛和尚のこの句はあまりにも有名ですが、一般的には、人間や世間のはかなさ、頼りなさを詠んだものと理解されています。み教えに照らしていただいてみると、無常、つまり私の思い通りにならない「いのち」であるから、老病死していくことに重ねて感傷的になるだけではなく、私の「思い」を、そのありのままの事実に合わせ、有限のいのちを、今どのように生きていくかを考えさせる一句とも味わえます。
お釈迦さまは、み教えを聞く者は「第一の矢は受けても、第二の矢は受けない」と説かれました(『仏教百話』)。例えば、病気の発症は、避けたいことではありますが、縁次第で起こるもので、私の「思い」だけでコントールすることはできません。この矢(一の矢)は、さとりの有無にかかわらず受けるしかありません。
しかしながら、その事実に対して、「どうして自分だけがこうなってしまったんだろう」「あのときこうしていれば、こんなことにならなかったかもしれないのに」といった具合に、いつまでもその事実に正面から向き合えずにいると、ますます苦悩を深めていってしまいます。
これが「二の矢」です。
ちなみに、病気という「一の矢」を受けたら、きちんと専門の医療者にお任せすることが大切です。「信じればその矢を抜いてあげますよ」という宗教には気をつけなければなりません。本当の宗教は「二の矢」を問題にします。
「二の矢」は「一の矢」に付随して自らの無明煩悩(思いにとらわれて道理を見失い迷うこと)によって、自らに対し放っている「矢」であると言えます。この矢を受けないためには、心を整え、冷静、客観的に与えられた状況を見つめて引き受けていくことが肝要なのです。
そういう私自身は、健康診断の結果を見る前から「二の矢」を受けて右往左往してしまい、矢を避け、抜くことの難しさを実感しています。
根を切ってもらった
こうした2500年前の仏教の考え方や生き方は、現代では、心理学をはじめ、経済学の分野でも語られていることを知りました。きっかけは、元官僚の経済学者で情報番組のコメンテーターとしても活躍されている岸博幸さんのインタビュー記事でした。
岸さんは、2023年に多発性骨髄腫というがんであることと、余命10年であることを告げられました。記事の中で、がんであると診断された時の心境を尋ねられた岸さんは、重病にかかると途方に暮れる人が多いと思うけれども、自分はそうならず、起きたことは取り返せない、後悔して治るならいくらでも後悔するけれども、後悔して元に戻らないから、それなら治療してもらって、いろいろやったほうがいいと思ったとおっしゃっていました。
こうした考え方は、行動経済学の「サンクコスト効果」という概念から導かれたそうです。サンクコスト(埋没費用)とは、「すでに支払ってしまい、取り返すことのできない金銭的・時間的・労力的なコスト」のことで、もう戻らないコストを取り戻そうとして、それに気をとられてしまって合理的な判断ができなくなる効果・呪縛のことを言います。岸さんはそうした呪縛に陥ることなく病気と向き合い、治療を経て退院され、現在はテレビ出演もされています。私には、仏教の実践的叡智の先駆性・普遍性を感じるお話でした。
病気のみならず、どうすれば「二の矢」を受けることのない生活、煩悩に振り回されない生き方を送ることができるのかを考えたときに、大阪の妙好人・物種吉兵衛さんのエピソードを思い出しました(『妙好人物種吉兵衛語録』)。
ある人が「吉兵衛さん、あなたのようになったら、もう腹は立たないでしょう」と聞いたら、「腹は立ちますよ。凡夫やもの。じゃが、(如来さまに)根を切ってもろうているから、実がならぬだけじゃ」と答えられたそうです。
これは、煩悩を消すことではなく、念仏申す生活の中で阿弥陀さまのお心に触れ続け、しっかりと煩悩具足の身と気づかせてもらい、きちんと自身の煩悩に向き合うことでさまざまな「一の矢」を受けても、その都度、煩悩に支配されて振り回されない生き方に転換される(二の矢は受けない)ということのお手本だと思います。
(本願寺新報 2024年04月20日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。