おぶつだんさんが来たよ-お念仏香る過程生活を象徴することば-
西川 正晃
岐阜聖徳学園大学教授 滋賀県彦根市・金光寺住職
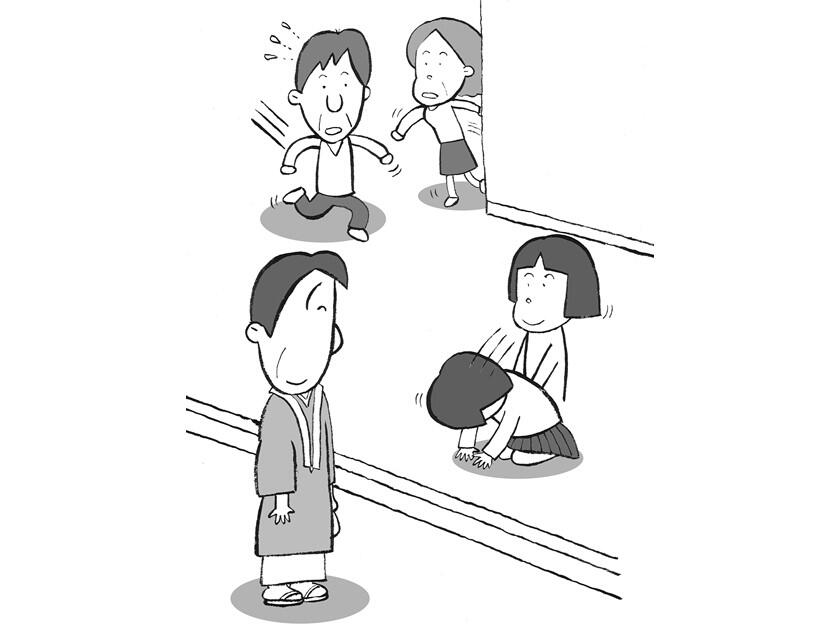
お念仏が染み込む
もう30年以上も前のことです。ご門徒のお宅に毎月のお参りにうかがいますが、あるお家では、まず、小学校低学年くらいの女の子が出迎えてくれるのでした。そして、その気配を感じて、奥におられる大人の方が出迎えてくださり、その子も一緒にお仏壇の前でお参りします。大人の方が留守の時でも、その子がいつも後ろに座ってお参りしてくれました。
子どもにとって、おつとめの間ずっと座っているのは、決して楽しい時間ではないと思うのですが、おつとめが終わって後ろを振り返ると、いつもその子は正座をして座っているのでした。念珠と聖典を手にしていたように記憶しているのですが、いつもその子とお参りの時間を一緒に過ごしていました。
ある日のこと、その女の子のお家にお参りにうかがうと、いつものようにその子が出迎えてくれました。その日は大人の方が在宅のようですが、いつまでたっても出てこられません。しびれを切らした女の子は、大きな声で「おぶつだんさんが来たよ」と叫んだのでした。
聞いてすぐには、私はその意味がわからなかったのですが、お参りに来た私のことを「おぶつだんさん」と呼んでいることがわかると、思わず笑ってしまいました。でも、その女の子は何がおかしいのかわからない様子でこちらの顔を見つめていました。そして問い返すこともなく、すぐにニコニコしてくれました。
染香人のその身には
香気あるがごとくなり
これをすなはちなづけてぞ
香光荘厳とまうすなる
(註釈版聖典577㌻)
親鸞聖人の『浄土和讃』の一首です。
もともと阿弥陀さまを敬う気持ちもなく、お念仏をすることもなかった人でも、いつしか阿弥陀さまのお徳が自然と染み渡り、お念仏をするようになっていく様子を「染香」と表現されています。
この染香人のたとえのように、普段から自然とお念仏に触れることで、私たちの生活は阿弥陀さまと一緒に力強く歩んでいくことができるのです。
夢にも思っていない
お仏壇と言えば、ご本尊である阿弥陀さまを安置する場所です。座敷やリビングなど、置かれる場所はさまざまで、お家によって大きさも違います。
女の子は、お仏壇のことを住職だと認識しているわけではないと思います。その子にとっての「おぶつだんさん」とは、お仏壇はもちろん、それにかかわる僧侶や仏事全体が「おぶつだんさん」なのだと思いました。ひいては、仏事だけでなく、普段からの生活に溶け込んだお念仏のある生活そのものではないかと感じました。
朝夕のおつとめはもちろん、誰かから何かをいただけばお仏壇に持っていく、ご飯を炊けばまずはお仏壇にお供えする、食前食後のことばを唱和するなど、そんな日常のあたり前の風景に、いつもお仏壇に安置されている阿弥陀さまがいてくださり、お念仏香る生活を象徴する言葉が「おぶつだんさん」なのだと味わわせていただいた出来事でした。
この女の子は、家の中にあたり前のように漂う念仏の香りを身に染みこませ、あたり前のように生活を送っていたのです。念仏の香りを染みこませた象徴が「おぶつだんさん」なのです。そんな生活が送れるこの女の子の姿を見て、素敵だなぁと素直に感じたのでした。
その女の子はやがて結婚して、お母さんになりました。先日、お父さまの一周忌法要の際に、子どもたちを連れてお参りされていました。家に着くと家族みんなで、すぐにお仏壇の阿弥陀さまに手を合わせておられました。お父さんとお母さんの後ろで手を合わす子どもの姿が、このお母さんの子どもの頃の姿と重なって見えるのでした。
その時、忘れていたこの「おぶつだんさんが来たよ」の出来事を思い出しました。
おつとめが終わった後のご法話で、その話をさせていただきました。話の途中までは、どこかであったおもしろい話だと笑って聞いてくださっていました。その女の子がお母さんの子どもの頃のこととは、ご自身も夢にも思っておられなかったようです。
「その女の子はあなたですよ」とお伝えした瞬間、驚きの声を上げられました。覚えてはおられませんでしたが、長年染みこんでいったお念仏の香りは、いまでも確かにそこにありました。
そしてその香りは、子どもにもいま染みこんでいっているのです。
(本願寺新報 2024年08月20日号掲載)
本願寺新報(毎月1、10、20発行・7/10、12/10号は休刊)に連載中の『みんなの法話』より
※カット(え)の配置やふりがななど、WEBサイト用にレイアウトを変更しています。
※機種により表示が異なるおそれがある環境依存文字(一部の旧字や外字、特殊な記号)は、異体文字や類字または同意となる他の文字・記号で表記しております。
※本文、カット(え)の著作権は作者にあります。