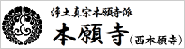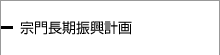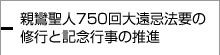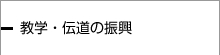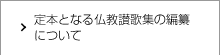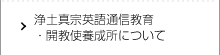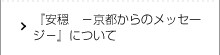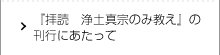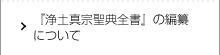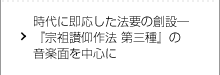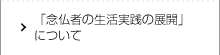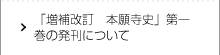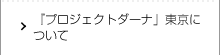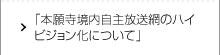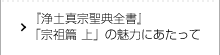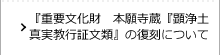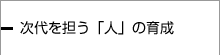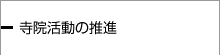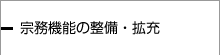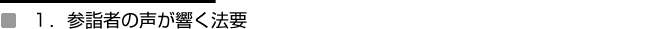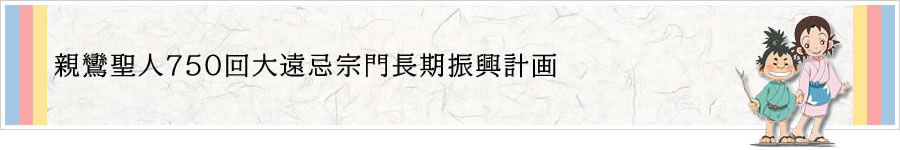
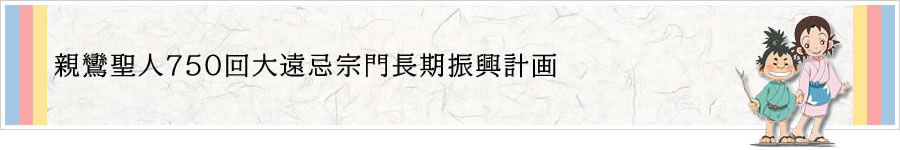
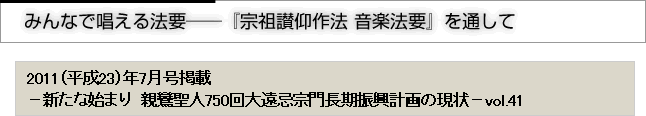
親鸞聖人750回大遠忌法要では、宗門長期振興計画「教学・伝道の振興」のうち、重点項目④「伝道態勢の整備」において制定となった『宗祖讃仰作法』と『宗祖讃仰作法 音楽法要』が、作法として依用されています。特に各期の後半、4日8座で依用された『宗祖讃仰作法 音楽法要』は、大遠忌で初めてとなる音楽法要です。その意味で、これからの時代における音楽法要のあり方を問うものでもありました。
本願寺派における音楽法要は、これまでにもご制定、依用されてきましたが、それらに対する反応──特に大衆唱和という観点において──は、決して肯定的なものばかりではありませんでした。
しかし今回の『宗祖讃仰作法 音楽法要』では、伝統的な「十二礼の節」による「正信念佛偈」はもちろんのこと、新たな譜による「頂礼文」や「和讃・念佛」、旧譜の「恩徳讃」による回向文と、ご文をお唱えするところのすべてが、参詣者による大唱和となっています。
とはいえ、そうした音楽法要を策定することは、「大衆唱和という観点での成功例といえるものがなかった」だけに、決して容易なことではありませんでした。
このような大唱和を実現するため、本願寺仏教音楽・儀礼研究所では、『宗祖讃仰作法 音楽法要』の策定に当たり、これまでに制定されてきた音楽法要の再検証から着手しました。なかでも役に立った情報が、蓮如上人500回遠忌法要で音楽法要が勤まったときのアンケート結果です。
そこから読み取ることができたのは、大衆唱和を現実のものとするには、何よりも「唱えたくても音楽的に難しい」という問題点でした。ちなみに、前回の大遠忌ののち程なくしてご制定となった『宗祖降誕奉讃法要』をはじめ、『御本典作法』、『音楽法要 おしょうしんげ』などは、いずれも讃歌衆が合唱でリードするようになっています。言い換えれば、専門的な音楽の教育を受けたものの存在なくしては、音楽法要の成立は困難である、ということです。
この讃歌衆がリードするというあり方ですが、おそらくキリスト教の典礼などが念頭にあったと考えられます。西洋音楽とともに発展したキリスト教の典礼ですから、西洋音楽を取り入れた法要を創出するというとき、それを範とすることは、ごく自然なことでしょう。
しかし、西洋音楽が日常の音楽となった日本社会とはいえ、西洋の社会がそうであるほどに、合唱することが一般的なわけではありません。その点についてどう対処するかが、今回の課題となりました。
学教教育で行われる音楽では、「楽譜を見て、正確に歌うこと」が、正しい音楽の学び方とされます。これまでの音楽法要では、おそらく、こうした考えに基づいていたと思われます。
しかし私たちは、決して楽譜からのみメロディーを覚えるわけではありません。むしろ、そういう日本人は少数派でしょう。カラオケで歌うときを思い出してみてください。そのほとんどは、聴いて覚えたものではないでしょうか?
そこでひとつには、耳に残りやすい=覚えやすいメロディーを、『宗祖讃仰作法 音楽法要』の中心とすることとしました。こうして生まれたのが、「頂礼文」と「和讃・念佛」のメロディーです。
しかし、新たなメロディーである以上、耳に残るメロディーとはいえ、数が増えると覚えなければならないので、負担になります。
そこで、伝統的な声明による作法に目を向けると、異なる作法でも、譜を共有している場合がありました。つまり大衆唱和を念頭においた音楽法要を策定する上では、すでに知られているメロディーによることも、ひとつの解決法といえるのです。その結果、旧譜の《恩徳讃》が、回向文として採用となりました。
さらに、広く知られているメロディーであれば、法要でそれを唱える人それぞれに、いろいろなイメージや思い出があることでしょう。それが仏教讃歌であれば、法要という場で唱えることで、自らの仏縁というものを考えずにはいられないのではないでしょうか。
このようにして策定され、ご制定となった『宗祖讃仰作法 音楽法要』は、大衆唱和という課題をクリアすることができたようです。しかし、法要における課題とは、それだけでなく、次の音楽法要策定に当たっては、時代の変化と共に、さらなる課題に直面することとなるでしょう。
ただ、この『宗祖讃仰作法 音楽法要』の例は、単に法要の策定だけに当てはまることではないと思われます。宗門の、あるいは各寺院の様々な活動においては、伝統を受け継ぎながらも、時代にあわせた新しいものが、常に求められることでしょう。本事例が、その参考になれば幸いです。