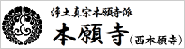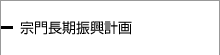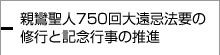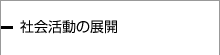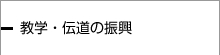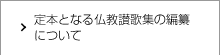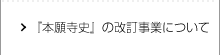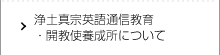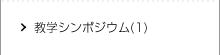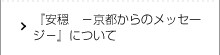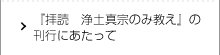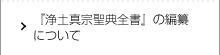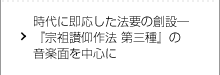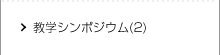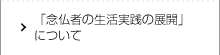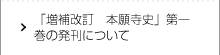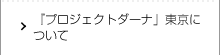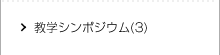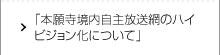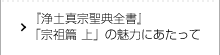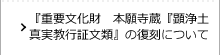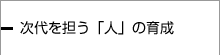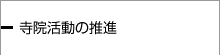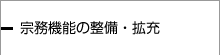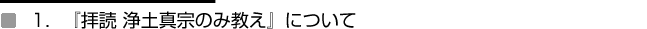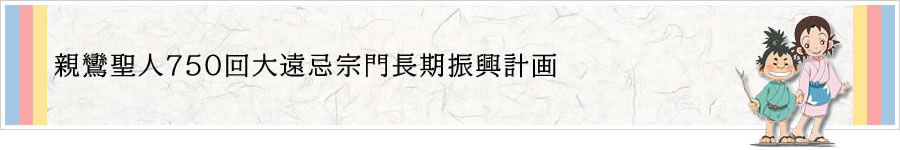
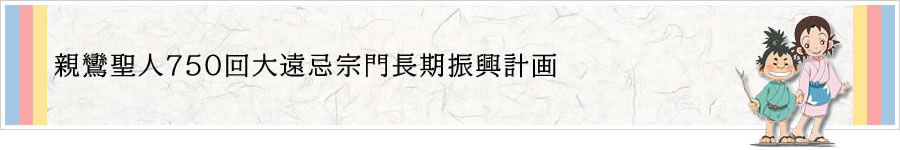
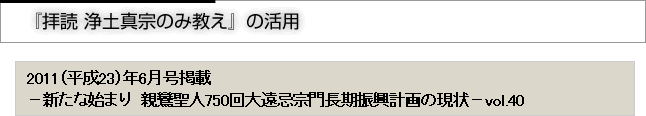
親鸞聖人750回大遠忌宗門長期振興計画「教学・伝道の振興」のうち、重点項目⑤「時代に即応する教学の振興」において、親鸞聖人750回大遠忌を記念して『拝読 浄土真宗のみ教え』が刊行され、丸2年が経とうとしています。この2年間で増刷は8刷を数え、刊行部数は20万部を超えました。この度の大遠忌法要では、記念布教などにおいても拝読されており、多くの方にこの味わい深い文章に触れていただくこととなりました。
『拝読 浄土真宗のみ教え』には、この大遠忌を記念して制作された、「浄土真宗の救いのよろこび」、「親鸞聖人のことば」、「折々のことば」が収載されています。これらは、「親鸞聖人が顕かにされた浄土真宗のみ教えを、現代の人々に親しみやすい表現によって示し、正しく領解した上で味わいを深めることのできる文章」となるよう、制作されたものです。
ここには、み教えが示された文章を声に出して読み、それによって理解と味わいを深めていくという、『御文章』、「領解文」等のよき伝統と精神が受け継がれています。文章を声に出してみると、目で追って黙読していたのとはまったく違う印象を受けることがあります。自ら声に出してこそ、そのことばの持っている響きや味わいを、より深く感じることができるのではないでしょうか。『拝読 浄土真宗のみ教え』にはそのような、声に出して拝読することでみ教えの味わいが深められる文章がおさめられているのです。
「浄土真宗の救いのよろこび」は、親鸞聖人が説かれた阿弥陀如来の本願のみ教えの要を、自らうけとめ、そのよろこびを述べていくものです。
そこには、短いながらも浄土真宗のみ教えの要である、阿弥陀如来の本願、南無阿弥陀仏の名号、信心、称名報恩、往生浄土、そして親鸞聖人のみ教えを広めていく伝道の心が織り込まれています。くりかえし自ら声に出して読むたびに、み教えに思いを傾け、味わいを深めることができるでしょう。
「親鸞聖人のことば」は、15章の文章で構成されています。15章それぞれのタイトルを挙げておきましょう。
人生そのものの問い(人間)/凡夫(煩悩)/真実の教え(釈尊と教典)/限りなき光と寿の仏(阿弥陀如来)/ 他力本願(本願)/如来のよび声(名号)/聞くことは信心なり(聞即信)/今ここでの救い(信の一念)/ 愚者のよろこび(二種深信)/報恩の念仏(利益)/浄土への人生(証果)/自在の救い(還相)/光の浄土(浄土の本質)/ 美しき西方浄土(西方浄土)/かならず再び会う(倶会一処)
タイトルからもうかがわれる通り、親鸞聖人のことばをもとに、浄土真宗のみ教えの要が親しみやすく示されています。
日々の勤行や、寺院でのご法座など、折にふれて声に出し、くり返し拝読いただくことで、み教えの理解と味わいが深められることと思います。
「折々のことば」は、年間の仏事とゆかりの深い行事、お正月、お彼岸、お盆、報恩講をテーマに、その由来と味わいについて述べられています。
その名の通り、折々にふれて読み返し、み教えの味わいを深められるように作られています。
ぜひ一度、日常の勤行、法事の場面など、さまざまな場面で、ご一緒にお参りの方と声を合わせて拝読してみてください。
声に出してみることで、いろいろな気づきがあるかもしれません。あるいは、み教えについて、語り合うきっかけになるかもしれません。
より深く浄土真宗のみ教えをよろこんでいただく一助になることでしょう。
 |
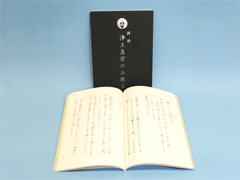 |
拝読の様子 |
『拝読 浄土真宗のみ教え』 |
『拝読 浄土真宗のみ教え』は、上述のように、大遠忌を記念して、より多くの方々と共にみ教えを拝読し、理解と味わいを深めるべく制作されたものです。その実現にむけて、発刊以降さまざまな普及活動を展開してきました。その一環として、多くの教区・組の『拝読 浄土真宗のみ教え』を用いた研修会に教学伝道研究センターの研究員が出講してきました。
研修会では、『拝読 浄土真宗のみ教え』の制作の意図、内容、構成等について解説し、内容の理解と味わいを深めていただくことができました。また、参加者のみなさまからも、アンケートや聞き取りなどで、『拝読 浄土真宗のみ教え』に対する感想や、用い方などの実情、ご意見をお聞かせいただくことにも努めています。その中から、普及にあたってのさまざまな現状と課題を見いだすことができました。今回は以下に、それらアンケートの調査結果の一部をご報告したいと思います。
まず、「『拝読 浄土真宗のみ教え』の刊行を知っていたかどうか」とお尋ねしたところ、どの研修会においても、七割以上の方が「知っていた」と答えられていました。これは、全寺院配付や本願寺新報、本願寺関係の機関誌を用いたさまざま広報活動が、一定の成果を上げて高い認知度をもたらしたものだと考えられます。
一方、「これまで、『拝読 浄土真宗のみ教え』を読んだことがあるかどうか」という問いに対しては、6割以上の方が「読んだことがない」と答えられ、さらに「これまで、日常の勤行や法座で用いたことがあるかどうか」についても6割以上の方が「用いたことがない」という回答をされました。しかし、本書についての研修会を受講した上で、「これから『拝読 浄土真宗のみ教え』を拝読していこうと思うかどうか」の質問に対しては、九割近くの方が肯定的に「用いたい」と答えられました。
これは、本書に拝読の一例が示されてはいますが、具体的に「どのように用いればよいか分からない」などといった疑問を持っておられた方が多くいたことを示すと共に、実際に拝読したり、研修会などによって「用い方」や「内容」についての理解が深まれば、十分多くの方に味わいを深め、よろこんで拝読していただける可能性をもつものであったことを示していると考えられます。
これらの意見を踏まえ、今後も積極的に研修会等の普及活動を行ない、より多くの方と共にこれらの文章を味わえるように努めて参りたいと考えています。